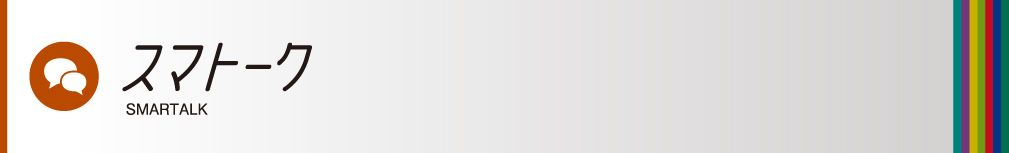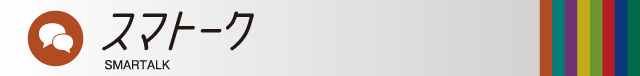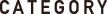- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年4月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
第30話・メロンつる割病 後編
〜農学博士・児玉不二雄の植物の病気の話
前回(第30話・メロンつる割病 前編)の続きです。
《伝染経路と発生環境》
病気にかかったメロンは枯れてしまいます。これを罹病残渣(リビョウ・ザンサ)といいます。つる割病の第一の伝染源です。残渣の中には、分厚い壁に包まれた病原菌の胞子(=厚壁胞子:コウヘキホウシ)が潜んでいて、メロンの根の先端(根毛)から侵入するのです。もう一つの伝染源は、種子です。病気に罹ったメロン種の中に、病原菌が潜り込んでいるのです。厚膜胞子は生存力が強く、長年にわたり土中でじっと潜んでいます。つまりメロンの連作は、発病を助長します。高温・乾燥年には発病が目立ちます。
《防除法》
1.施設栽培では、太陽熱や薬剤による土壌消毒を行います。
2.健全種子を用い、種子消毒を行います。
3.無病苗を定植し、病株は見つけ次第除去します。
4.この病気に対して、抵抗性品種が開発されています。しかし抵抗性品種に打ち勝つように変異した病原菌グループ(=レース)も出現していますので、慎重な品種選択が必要です。
《病原菌と寄主範囲》
この病原菌は、メロンにしか感染しません。病原菌が感染・発病させることのできる植物のグループを寄主範囲といいますが、この菌は寄主範囲が一つということです。名前はFusarium oxysporumf.sp. melonis(フザリウム・オキシスポーラム・フォルマ・スペシャーリス・メロニス)。全世界共通の呼び名です。
今回のキーワード:ツル(蔓)と茎、スポロドキア、厚壁胞子、レース
■執筆者プロフィール
児玉不二雄 Fujio Kodama
農学博士。北海道大学大学院卒業後、道内各地の農業試験場で研究を続け、中央農業試験場病理科長、同病虫部長、北見農業試験場長を歴任。その後、北海道植物防疫協会にて、会長理事等を務めた。
45年以上にわたって、北海道の主要農産物における病害虫の生態解明に力を尽くし、防除に役立てている植物病理のスペシャリスト。何よりもフィールドワークを大切にし、夏から秋は精力的に畑を回る。調査研究の原動力は、“飽くなき探究心”。
※本コラムの内容は、2009年よりサングリン太陽園ホームページ 「太陽と水と土」に連載しているコラムを加筆・修正したものです
※写真:著者
![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header.png)
![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header_sp.png)