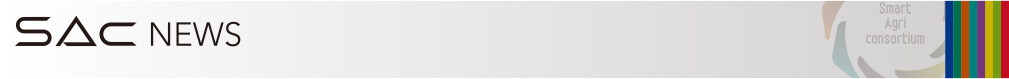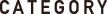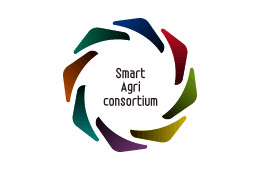- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
農研機構がバイオ炭の農地施用による炭素貯留量を簡便に算出する手法を開発
農研機構は、秋田県立大学、立命館大学、和歌山県工業技術センターと共同で、日本産業規格(JIS M 8812)の分析値を活用し、炭化温度および土壌炭素貯留量を算出する手法を開発したと発表しました。この手法を用いると原料の種類に関係なく炭素貯留量を簡便かつ正確に計算できるため、バイオ炭の普及促進や炭素クレジット創出の効率化が期待されています。
バイオ炭とは、バイオマス(生物由来の有機物)を燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350°C以上の温度で加熱して作られた固形物のことです。バイオ炭の炭素は難分解性の特性があるため、土壌に施用し炭素を貯留する効果的な手法として国際的に認められています。農業分野でもバイオ炭を農地へ施用することが気候変動の緩和や土壌保全に貢献すると考えられており、CO2削減のクレジット化の手段としても注目されています。
バイオ炭を活用した炭素クレジット創出には、土壌へ施用する炭素量に加え、炭素の固定効果を評価する必要があります。その手法の一つである2019年IPCC改良ガイドラインに沿ってバイオ炭による土壌炭素貯留量を算出するには、投入バイオ炭の重量、当該バイオ炭の有機炭素含有率(Fc)および100年後の炭素残存率(Fperm)を用います(炭素貯留量(トンCO2)= 投入バイオ炭の重量(トン、乾重)× Fc × Fperm × 44/12)。同ガイドラインでは有機炭素含有率および100年後の炭素残存率のデフォルト値が提示されていますが、用いる原料の種類や炭化温度によってこれらのデフォルト値は異なります。特に、炭化温度が不明なバイオ炭や、ガイドラインに明記されていない原料を用いる場合、これらのデータを取得するためには、時間と費用がかかる元素分析などの測定が必要であり、バイオ炭を活用した炭素クレジット創出における事業者の負担となっていました。
今回、新たに開発された手法では、元素分析を行う代わりに、石炭の品質評価に用いられる日本産業規格(JIS M 8812)を応用し、バイオ炭の工業分析値(揮発分(VM)や固定炭素(FC))を用いて、炭化温度や農地施用による炭素貯留量を算出します。JISに基づく工業分析は日本国内の公的機関で実施可能であり、測定精度が確保されています。さらに、この算出式を原料ごとに研究機関等が作成・共有することで、バイオ炭の品質評価プロセスの効率化が進み、結果としてバイオ炭による炭素クレジット創出の効率化が期待されています。
詳細は、農研機構のホームページをご確認ください。
![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header.png)
![[SAc WEB]SAcが運営するスマート農業情報サイト](/common/images/header_sp.png)